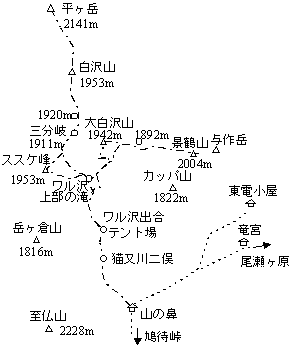|
山スキー 尾瀬〜平ヶ岳,景鶴山
|
|
【月日】 99年4月29日(木)〜5月2日(日)
| |
【メンバ】単独
| |
【装備】 山スキー,兼用靴,シール,スキーアイゼン,冬テント,シュラフ,食料3泊分
|
【参考】 2.5万図「至仏山,尾瀬ヶ原,平ヶ岳」,山スキールート図集1,
FYAMAALP 山岳スキー2560,1776,岳人98年2月号,山登魂ホームページ,他
|
| 年月日 |
1999年4月29日(木) |
| 天気 |
曇り時々雪 |
| タイム |
練馬(4:40)=沼田IC(6:10)=鳩待峠(7:50/8:57)…山ノ鼻(10:13/10:39)
…二俣(11:39/12:04)…ワル沢出合テント場(12:04 偵察〜13:05)
|
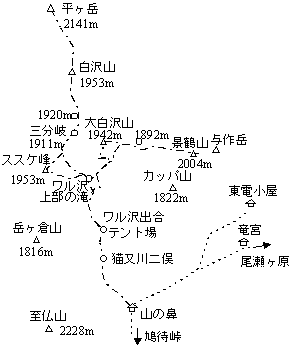
|
GW前半は、尾瀬から平ヶ岳へと向かうあこがれの山スキーロングルートにトライ。同時に尾瀬にあってなかなか登れない山、景鶴山も目指すプランにした。連休前に風邪をひいてしまい、体調が完全には復帰しないままの出発となった。
早朝練馬発、沼田のコンビニで買い出しの後、鳩待峠へ。日帰りのボーダーやハイカーがちらほら、まだ一段下の駐車場には余裕がある。雪の量は、4年前に来たときよりやや少ない感じ。先の様子がわからず、トレースをツボ足でたどる。途中何回かスキーをはいてみるが、すぐ雪が切れ木道が出ているのであきらめてまたツボ足(頑張ればスキーをはいたまま通過も可)。平坦な尾瀬ヶ原の一端に出てからは、のんびりシール歩行で山ノ鼻へ。山小屋開業直前とあって、ハイカーが数パーティーいるだけのオフシーズン最後の静けさが漂う。天気予報に反して時折雪も舞い、至仏の頂上は雲の中だ。
一般道をはずれて猫又川の右岸沿いに奥地へ向かう。スキートレースも消えがちで、人の気配が無くなる。平坦な雪の台地に縦横の亀裂が入り、湿原が顔を出し始めている。まだ亀裂に進路を阻まれることはないが、亀裂が一本の線につながり人が立ち入れなくなるのも、まもなくのこと。今の時期だけ、容易に足を踏み入れることが許された世界だ。
沢の蛇行で2度ほど軽く高巻くと猫又川の二俣。かろうじて残ったブリッジで対岸に渡ることができた。重荷に体調も不完全なので、尾根へ取り付く急斜面を重荷で登る元気も無く、最近のFYAMAALPのレポートと同じ左俣に入るルートを取る。なるべく沢をつめ、水の得られる場所で幕営したい。沢の左右へブリッジを何回か渡っていくと、谷の幅も狭くなり、ワル沢出合の滝あたりが沢筋を進める限界。滝の手前、左側の台地にほどよいテント場を見つけ、時間は早いが天気も悪いことだし、ここで幕営することにした。沢の水が得られ、コメツガに囲まれ、なかなか快適な場所(滝の音が少しうるさいが)。午後から夜にかけ、雪が降り続いた。自分だけのこの秘境で、昨日までのあわただしい仕事からの解放感に浸っていると、午後のひとときもあっと言う間だ。
| 年月日 |
1999年4月30日(金) |
| 天気 |
晴れ |
| タイム |
テント場(5:05)…1911m三分岐ピーク(7:09/7:29)…白沢山(8:37/8:45)…平ヶ岳(10:06/11:04)
…三分岐(12:50)…ススケ峰(13:29/14:09)…テント場(15:07)
|
今日からは好天だ。平ヶ岳への往復へ挑戦。ワル沢出合滝の先、右のブッシュ混じりの急斜面を、早朝のクラストした雪を慎重にツボ足で登る。傾斜が緩くなり、シール登行で地図とにらめっこしながら進む。何とPRO-TREKの電池が弱って高度計が使えない。三種の神器の1つが使えないのは痛い! 窪地や短い急斜面に進路を阻まれわかりにくい。地形の特徴をひろって進む。ワル沢の右岸斜面を単調に登るようになるとルート探しは楽になる。
大白沢山
 ワル沢上部、ススケ峰鞍部への登りより望む
ワル沢上部、ススケ峰鞍部への登りより望む
|
ワル沢二又部の滝の右岸上部に出たところで、雪が切れて岩が露出していて進路に悩む。左へ少し登って急斜面を斜めにもどるように上がると、再び沢の右岸を進めるようになった。あとはススケ峰の右の鞍部目指して登る。右には大白沢山が、気持ちよさそうな斜面をさらけ出している。次第に展望が開けてきて、尾根にたどり着く。稜線は結構雪の凸凹が大きく、それを避けて右側をトラバース気味に三分岐の1911mピークへ。展望を楽しむのもつかの間、気合いを入れて、平ヶ岳への長い稜線歩きへ。
昨夜の雪に先行のスキートレースは消されている。次の1920mピークは稜線と左側はブッシュが出ているので、右側をトラバースしていく。急斜面で樹木が切れているので緊張した。雪崩にも警戒。
鞍部への下りは雪庇と雪の凸凹があり、注意してシール滑降。白沢山へはだらだらした緩い登り。白沢山からの下りも雪庇注意。裂け目をまたぐところもあった。さらに平らな雪原を歩き、最後の急登をジグザグにこなすと、だだっ広い雪原に1本の棒が立つだけの頂上(最高点)に到着。
平ヶ岳
 平ヶ岳へ続く稜線を大白沢山から望む
平ヶ岳へ続く稜線を大白沢山から望む
|
あの辺の玉子石も今は雪の下に埋まっているのか。
日本100名山の97座目を山スキーで征服できたのも感激だ。しばし雪の上に倒れ寝転がる。そして360°の展望を満喫。日光尾瀬はもとより、会津駒と三岩の先に,坪入山から会津朝日方面へ,あるいは中ノ岳から荒沢岳へ,あるいは中ノ岳から巻機山を経て谷川連峰へと続く未知の尾根と山々に見入る。
昨夜の雪でコンディション良く、頂上直下の滑降は最高! 平坦部は登り返しを少なくするようにピークの右を巻き気味に行く。白沢山手前の鞍部で再びシール付け、ここからはほぼ稜線通しに往路をたどる。途中3人組に会った(この日会った唯一のパーティ)。1920mへの登りかえしは長く、雪の凸凹で出来た壁を越えるのが疲れる。1920mピークを再び緊張してトラバースすると、今日の行程もやまを越え、平坦な三分岐直下でのんびりする。
先のパーティーは大白沢山の北を巻いて来たらしい。平ヶ岳を目指すにはその方が効率良いらしい。私は大白沢山は明日にして、見るからに快適そうな斜面を持つススケ峰へ寄っていくことにする。今朝登ってきた鞍部へシール付きで下ると、ススケ峰を往復したシュプールがあった。つらい登りかえしを頑張る。急登が終わってから頂上へはさらに平らな尾根を10分ほどたどる。至仏と笠ヶ岳がぐっと近づく。シールを外して、お日様を浴びながらしばし昼寝だ。
会津駒ヶ岳
 平ヶ岳へ向かう尾根より望む
平ヶ岳へ向かう尾根より望む
| 至仏山とススケ峰
 三分岐1911m付近より望む
三分岐1911m付近より望む
|
むっくと起きて下りにかかる。往路をもどらず気持ちよさそうな斜面に飛び込む。樹林もまばら、斜面もなだらかで、気ままな滑りを楽しむ。滝付近を目指して急斜面をトラバース気味に沢へ下りていくと、私の往路のトレースにぶつかることができた。あとは往路を忠実にたどれば良いはずだが、朝はクラストしていたので明瞭なシュプールが無く、平坦地で少し迷う。見覚えのある対岸の岩壁が良い目印になった。朝ツボ足で登った最後の急斜面は、ブッシュに阻まれつつも何とかスキーで下って帰幕。体調が今一つで予想以上に疲れたものの、充実した一日であった。
| 年月日 |
1999年5月1日(土) |
| 天気 |
晴れ |
| タイム |
テント場(6:00)…滝(6:58/7:18)…大白沢山(8:28/8:56)…景鶴山(10:31/11:22)
…池(13:14/13:28)…テント場(14:06)
|
昨日のルートをたどり、ワル沢上部の滝の前まで来ると単独男性に会う。景鶴には一昨日登ったそうで、今日はススケ峰へ向かうそうだ。情報交換し、私は昨日のルートを離れ、滝の右の尾根へ進むことにした。一度広い窪地へ下ってから急な樹林帯の登りになる。昨日の3人組と見られるスキートレースに出会う。急登が一段落して平坦地へ。この先の大白沢山への登路も選択の余地あり。直進すると崖に阻まれそうなので、トレースはずれて左の尾根の末端から取り付くことにした。少し遠回りだが雪崩の危険は無い。頂上へはコメツガもまばらな快適な斜面が続いている。傾斜がきつくなると、雪が締まってシールが効かなくなり、スキーアイゼンを装着。傾斜が緩くなって平坦な尾根に出る。左へ稜線漫歩しばしで大白沢山頂上。少し樹木が邪魔になるが、昨日歩いた平ヶ岳への稜線など周囲の展望良好。
景鶴山
 大白沢山から景鶴へ向かう尾根より望む
大白沢山から景鶴へ向かう尾根より望む
|
大白沢山の平坦部から少しヤセ尾根を下る。鞍部からは稜線上にスキーの跡があった。まず1892mピーク南側を巻く。その後はなだらかな樹林帯の散歩気分。1898mピークで少し昼寝、昨日より距離も短いので気が楽だ。正面に独特のプリン形突起の景鶴山が近づく。頂上手前で急斜面になる岩場の下でスキーデポ。ここから稜線は雪が切れて進めず、尾根の北側の樹林中を巻いていくトレースをたどる。急斜面をブッシュをつかんで登り再び稜線へ。所々地肌が出たところは、ヤブ道や岩場。小さく上下していくとスキーデポから20分程で、標識のある山頂に出た。昨日の日付のプレートも置かれていた。
眼下に景鶴沢が尾瀬ヶ原へ落ち込んでいる。既に雪が消えてもろい岩肌が見えており、沢沿いの登行は厳しいだろう。尾瀬ヶ原の雪原を蛇行する黒い川筋や山小屋が手に取るように見下せる。至仏や燧から会津駒にかけては展望が良いが、反対の平ヶ岳方面は樹林にさえぎられ良く見えない。山頂としては平凡だが、300名山であるなしに関わらず、今回訪れた大白沢山やススケ峰などの奥まった寂峰と同様に、私にとって非常に興味を引かれ、登らないわけにはいかない山であった。頂上だけでなく山全体を少しでも多く知ることがとても楽しい、そんな感じなのだ。
東電小屋の方から登ってくる人の声がするが、姿は見えない。先に失礼して下山にかかる。カッパ山方面を放浪する手もあったが、前記のように高度計が使えず、下手に下るとテント場へ戻るのに沢の横断で難儀しそうであり、稜線上を忠実に戻ることにした。大白沢山の手前の鞍部から南西の小ピークへ登り、先行のシュプールからあまり外れないように注意して、窪地の沼のところまで林間滑降。まことに素晴らしいの一言であった。ワル沢をブリッジの所で渡って、右岸を登り気味に進んで、自分の朝のシュプールに出た。あとは昨日と同じルートをテント場へ。何回通ってもわかりにくいが、さすがに昨日ほどは迷わずブッシュの急斜面の上に出る。今回はスキーを脱いで下りた。頑張れば今日のうちに鳩待峠へ行けなくもないが、お気に入りのベースでもう一泊し、残りのウイスキーや乾燥食料(チゲ鍋やポテトサラダなど一応豪勢)など平らげながら目的の達成を祝った。
| 年月日 |
1999年5月2日(日) |
| 天気 |
晴れ |
| タイム |
テント場(6:10)…二俣高巻き(6:30〜7:00)…山の鼻(7:52/8:04)…鳩待峠(9:34/10:23)
=戸倉温泉(10:48/12:10)=沼田IC(13:20)
|
3泊もしてすっかり愛着のわいたテントサイトにも別れを告げ、猫又川沿いに下る。二俣にはテント3張り、日帰りの人にも会う。来たときには有ったブリッジが崩れ、沢を渡れなくなっていた。渡渉した方がてっとり早いが、インナーが濡れるのが嫌で、ツボ足で上流に登りかえしてブリッジを渡って右岸を高巻いて来たので、だいぶ時間を食った。
やはりこの二俣から尾根に取り付く人が多いようだ。この先は私が入山した時とは一変して、山の鼻からクロカンやハイキングの踏み跡がしっかりできており、この日もたくさんの人が登ってきた。山の鼻に来ると、もはやハイカーだらけの別世界だ。スキーヤーは肩身が狭くなる。木道が現れたところで、スキーを背負って、重荷に喘いで鳩待峠へ登りを頑張ることになる。これが結構長く、きのう来たらバテバテだったことだろう。
峠で一服してから荷物を車に積んでGW後半の山行へ出発。諸事情を考慮し、予定を変更して毛勝山へ向かうことにする。駐車料金を取られたが1日分\2500で済んだ。道路も来たときとは一変し、駐車場に入れない車が延々と路上駐車している状態。戸倉温泉で入浴+天ぷら蕎麦で元気をつけて、いざ毛勝山へ。
|