| 南ア深南部 寸又峡温泉〜黒法師岳〜水窪 (滑落事故に遭遇) | ||
| 【月日】 98年11月21日(土)〜23日(祝) | ||
【メンバ】単独
|
【装備】 1人用テント(夏仕様),シュラフ,炊事具食料,水Max4L,皮登山靴,スパッツ
|
【参考】 アルペンガイド「富士山周辺、駿遠の山」,1/50000地形図 井川/満島,岳人97年7月号, | FYAMATRK中部南766,726,649,FYAMAALPバリエーションハイキング中部96,他 |
| 年月日 | 1998年11月21日(土) | |
| 天気 | 晴れのち曇り,風強い | |
| タイム |
横浜(4:55)=(JR)=三島(6:27/6:45)=(こだま)=静岡(7:11/7:22)=(JR)=金谷(7:55/8:10) =(大井川鉄道)=寸又峡温泉(9:55/10:00)…登山口(10:45)…栗ノ木段(12:02) …シオッカレ(13:00/13:20)…前黒法師岳(14:17/14:45)…林道ヘリポート(16:15) |
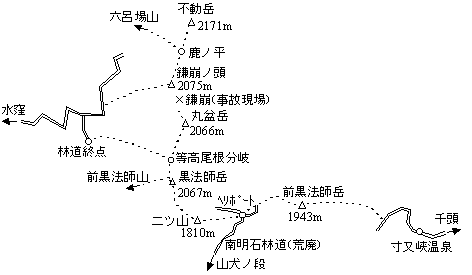
|
昨年の山犬ノ段周辺 に続いて、南ア深南部 に足跡を延ばそうと、寸又峡温泉から黒法師岳方面へ、
メインの縦走路を行けることろまで行こうと計画を立てた。当初3連休+休暇1日で4日間を企んだが、
休暇が取れず3日間の計画になった。これだと鎌崩(カマナギ)を越えて不動岳まで行けば上々かなと考えていた。
過去のReportによると水に不自由しそうなので余分に準備していく。
初日は目一杯早朝発で寸又峡到着が10時。前黒法師岳を越えてヘリポートの
テント場までを目指す(結構きつい)。ゲートの先で登山届けの提出を求められる。今日は三組入山してるとのこと。
また日帰り観光客に任意で協力金寄付を呼びかけている。北風が吹き付け寒い中、三連休とあって
虹の吊り橋散策の多くの観光客に混じって歩き出す。時々「前黒ですか、凄いですね」と声をかけられる。
登山口からいきなり急な心細い道となる。石垣が積まれた集落跡を登っていき、伐採された尾根に出ると
風当たりが強く寒い。樹林帯に入り風を避けられるようになりホッとする。途中二人組二パーティに会うが、
いずれもこの寒さにみぞれにも見舞われ、頂上まで行かずに引き返したという。シロッカレに登り着くと、
気温も下がり手が凍えそうになる。結構薄着だったのであわてて冬装備を取り出す。頂上まで行ってきた
単独の女性に会い、部分的な積雪の中頂上に到着。コメツガに覆われ展望のない平凡な所。
ここからが深南部の真髄に近づいていく。道は不明瞭になり指導標も少なくなる。頂上から目印を確認して、
右よりの踏み跡に入る。赤布など目印はまあ豊富。ピークを越えて平らになったところで、間違えて
北西方向に伸びる尾根の踏み跡に入ってしまう。目印が無くなり、磁石と黒法師らしきピークの方角から、
おかしいとみて引き返すと、道が左に直角に曲がるところで間違えたことが判明。注意すると目印もあったが、
やはり間違えやすい所だ。
踏み跡をひろって下っていくと、荒れた林道の終点に出た。ここからは林道跡を歩く人が多いようだが、
道無き尾根上を忠実に進んでみると、薮もなく一つピークを越えて、目的のヘリポート広場に到達。
スペースはとても広く、テントを張る場所には事欠かない。風を避けられる切り崩し際付近で幕営。
山犬ノ段方面の夕暮れを見て、鹿の声だけが響く静かな一夜を過ごした。
| 年月日 | 1998年11月22日(日) |
| 天気 | 晴れのち曇り一時雪 |
| タイム |
林道(6:45)…二ツ山(7:34/7:39)…コル水場無し(8:18/8:50)…黒法師岳(9:34/10:00) …等高尾根分岐(10:27/10:30)…丸盆岳(11:20/14:20)…丸盆岳南側テント場(14:40) |
テントは夏仕様のため寒くて、寝むりは浅かった。でも風も弱まり快晴の良いコンディションだ。
広場の鞍部からは、朝日が当たる黒法師岳、丸盆,不動岳,遠方に池口岳から光岳方面が望めた。
ガイドに記述ある水場を確認しに、林道を10分ほど進んでみるが、一向に水の気配無く引き返す。
 南明石林道終点のヘリポート広場より望む
南明石林道終点のヘリポート広場より望む
|
黒法師岳への登りは鹿道が交錯しルートがわかりにくい。私も道をはずれてしまい強引に登っていくと 正しい道に出た。鞍部の標識通り左に巻くようにルートがとられているようだ。この辺で下ってくる 複数のパーティーに会う。水窪側から黒法師三山を3日で縦走する人が多いようだ (寸又峡から登るのは確かに変わっていると自分でも思う)。
積雪を踏みしめて頂上に到着。コメツガに囲まれた小広い平坦な頂上は、展望は無いものの 落ち着いた良い雰囲気。しばし誰も居ない頂上を独占、何かこれで満足という気になる。 最南緯度の2000m峰で三角点が×印なのも有名だとは後で聞いた話。少し下ると前黒法師山分岐 の所で、前方に鎌崩から南ア本峰に続く展望が開けて素晴らしい。ここで等高尾根から日帰りで 登ってきた二人組に会った。
 この直後、遭難同行者と遭遇
この直後、遭難同行者と遭遇 |
このとき、前方のピークに1人の登山者が登り着き、私を見て、「助けて!1人滑落、SOS!」 などと叫ぶのが聞こえた。これで山行は中断となった。私はどうしたものかと思いながら、 彼に近づこうと崩壊沿いの道を注意して下っていき、やがて登ってくる彼に会った。 息を切らせ動揺しながらも、鎌崩で同行者が100m程滑落し、出血多量で危険な状態にあること、自分では 救助不可能のため救助を求めて登ってきたことを伺う。私もザイルや無線等の装備は無いため、 とにかく連絡をとるために先に戻ることにした。丸盆岳の頂上に戻ると、先ほど黒法師頂上で会った 男性二人がいて、事情を話すと一人がアマチュア無線機を持っているのでここから連絡をとってくれる ことになった。もう一名は地上から連絡のため先に下山、私は幕営具があるので、何かの時に手伝えるように この場に残ることになった。
滑落の同行者も登ってきて、改めて詳しい話を聞く。彼がFYAMAのがんじゅさんで、遭難者が緑山さん ということも判った。彼らも危険が有れば引き返すつもりでいたという。滑落場所は、丸盆岳と鎌崩ノ頭との 中間の最低鞍部から、いわゆる鎌崩の"低巻き"ルートで100mほど東斜面をトラバースした付近で、ホールドにした木の枝が折れたはずみでバランス を崩し、ほぼ垂直な斜面から約100m滑落。この時点では付近に積雪は無かったという。がんじゅさんは 別の斜面を下降して緑山さんの所まで下ることができた。緑山さんは呼吸はしているものの意識不明で、 頭などからの出血ひどく、滑落した岩には点々と血の跡がついていたという。 頭が下向きで止まっていたので、緑山さんのリュックをはずし、 頭を上にしてマットとシュラフに体をくるんで寝かせ、意識が戻った時のためにそばにリュックを 残しておいた。体重の重い緑山さんを移動するのはこれだけでも大変だったそうで、ズボンが血だらけになった。 このあと稜線に戻る途中、がんじゅさんも一度滑落しかけたが木に引っかかって止まったという。 一瞬自分もこれで終わりかと思ったという。
ハンディ機での連絡は結構手間取った。非常時のアマチュア無線の交信がどう行われていくか 一部始終を聞くことができたのは貴重な体験でもあった。はじめ山犬ノ段の蕎麦粒山で交信していた 人が受信、その後浜松市の方に受信され、電話で警察に連絡を入れてもらうことができた。 すぐに清水からヘリが飛ぶとの回答が無線を通して連絡入る。その後電池切れのため、 交信がままならなくなった。今は携帯電話の方が便利と言えよう(ただし圏外となる危険性はあり)。
頂上にヘリのホバリングで救助隊が到着すれば、今日救出に向かうことも可能かとも考えたが、日没が早いため 時間的に厳しい。午後1時を過ぎ、ようやくヘリが付近に飛来。もう1名登ってきた単独者を加え、 4人で一生懸命手を振るが、付近を旋回するだけで戻ってしまう。あいにく天候も悪化してきてガスがかかってしまった。 無線連絡だけでは詳しい情報は伝わっていないようで、警察も場所は特定できていないようだ。
午後2時頃日帰り装備の2名が下山。雪も降ってきたので、私とがんじゅさんは南側の草原でそれぞれテントを 張って待機することにした。最初風を避けて稜線を少しはずれた樹林中の鹿のヌタ場にテント張ったが、見つけにくい かと思い直し、もう少し下った道の脇のテント場に移動した。道からもヘリからも見つけやすく、風当たりも 避けられる絶好のポイントであった。雪が降ったおかげで残り少なくなった水は補充できた。
その後ヘリの飛来もなく、 二人で雑談も交えて話しながら夜を迎えた。私も今回緑山さんのReportを印刷したものを参考に持参していたのだから奇遇である。 ミニヤコンカの奇跡を思いだし、ひょっとしたら緑山さんが自力で歩いて来るなどという可能性も考えたが、 そのような奇跡は無かった。ずっとラジオを聞き続け、7時のニュースのローカル版で遭難の報道あり。 現場付近は雲が厚く詳しい状況がつかめなかったので、明日夜明けを待って再度ヘリで捜索するという内容。 場所を不動岳と報じたので気になったが、下山した方からも詳しい連絡をしていただけるから問題ないと考えた。
| 年月日 | 1998年11月23日(月) |
| 天気 | 晴れ |
| タイム |
丸盆岳南側テント場(8:00)…丸盆岳(8:35/8:55)…テント場で救助隊待つ(9:10/12:18) …等高尾根分岐(12:43)…林道終点(13:50/13:55)…中小屋ゲート(15:15)…吊り橋(16:30/16:35) =(ヒッチハイク)=水窪(17:00/17:41)=豊橋(19:45/19:52)=新横浜(21:53) |
早朝霧がでていたが、明るくなると共に霧が流れて晴れてきた。霧氷が日に輝き、後方に黒法師岳,
前方に丸盆岳から先の山々と素晴らしい朝の景色。雪と霧氷で山々はいっそう白さを増した。
あのコルの近くに緑山さんが居る、という事実は厳粛に受けとめなくてはならない。でも美しい山の景色
を見ていると、そんな話は信じられなくなってしまう。 後方は霧氷と黒法師岳
後方は霧氷と黒法師岳
7時過ぎに私が朝食を食べようとしているとヘリの音。これで朝食どころではなくなり、2人で一生懸命
手を振る。付近を偵察するように旋回したあと、高度を下げながら我々の上空を旋回し、平坦な草原の上で
ホバリングして救助隊の方3名が次々にロープで下りてきた。これでやれやれ、といってもこれからが大変だ。
必要な装備をまとめ、テント食料はここにデポして、8時に現場へ出発。私もできれば手伝って欲しいと
いわれ同行した。丸盆岳頂上から先は積雪のため危険度が増しており、私はテントのところで待って、地上から
登ってくる救助隊へ状況を連絡することを頼まれ、ここで別れることになった。
テントに戻り、がんじゅさんは大変だなあと同情しながらも、のんびり朝食を取り直しつつ待つ。
10時半頃にまたヘリが飛来するが付近を旋回しているのみ。11時45分にやっと救助隊4名が到着(遅いなあ)。
私から説明の後、その後の状況を聞くが、あまり進捗していないみたいだった。無線が通じにくく詳しくは
彼らも判っていなかった。アイゼンを装着し、彼らもここに荷物デポして出発、ようやく私も解放されることになった。
車が無いので、最悪は水窪ダムまで林道を歩かねばならず、急いでテント撤収して出発。昨日通過した崩壊部の急登、登高尾根上部
の急降下など、積雪の為慎重に通過。雪がなくなると笹の切り開きを一気に下る。等高尾根登山口から、崩れかけた林道を
しばらく歩くと六呂場山方面に延びる林道と合わさる。ここには今回の遭難で警察関係の車がたくさん入っていた。
車の中にいた人は待ちくたびれた表情だった。まだ稜線上空をヘリが旋回し続け、作業が続いていると思われた。
私は今日中に帰るため、林道をひたすら下る。中小屋ゲートから一般車が入れるようになる。ゲート前には数台
駐車してあった。緑山さんの車も確認。まだ誰か下山してくる様子なく、途中で拾ってもらうことを期待して
歩き続ける。さらに1時間以上歩いて、麻生山登山口の吊り橋のところで、麻生山へ日帰りで登ってきた
浜松の単独行氏に会い、水窪駅まで乗せていただけることになった。これで波乱の深南部行も幕を閉じることになった。
少し前にも黒法師岳から山犬ノ段方面を目指した単独女性が道に迷うという遭難があり、深南部も決して
侮れない。やはり登山道の整備状況が悪いことが危険につながっているようで、それが深南部の魅力でもある
ゆえに要注意である。
[追記]以下はがんじゅさんからの情報です。救助隊と滑落現場まで到着後、そこから下は
ザイルが必要な状況で、がんじゅさんは後発の救助隊への連絡を依頼されてそこで待っていました。
救助隊の人がザイルを使って現場に下り、緑山さんの死亡が確認され、午後1時にがんじゅさんにも
その情報が伝わりました。現場付近の状況は前日と一変して雪と凍結の危険な状態になっており、
その日は緑山さんの遺体を稜線まで上げる事が出来ませんでした。翌24日、夜明けとともに現場に向かい、
稜線まで引き上げる作業に入り、午後12時30分頃稜線に遺体が到着、午後12時53分ヘリにて
御家族のもとへ搬送されました。
| 国内の山行レポートのメニューに戻る |
| トップメニューに戻る |